講座づくりをしていると、楽しいこともたくさんあるけれど、
それと同じくらい、地味に頭を悩ませる問題にもぶつかります。
新しい講座を企画するたびに、
こんな服を作りたい、あんな布を使ってみたい──と
あれこれ想像する時間は至福のひととき。
だけど、それを“人に教える”という立場で考えたとき、
「これ、ちゃんと許されてる使い方なのかな?」と、
ふと不安になる瞬間があります。
とくに今回、大きく立ちはだかったのがこのテーマ。
「市販の型紙、講座で使っていいのか問題」です。
洋裁を趣味で楽しんでいるときにはあまり気にしなかったことも、
講師として、人に教えてお金をいただく立場になると、
見えてくる世界が変わってきます。
「いいじゃない、誰にも迷惑かけてないし」と言いたい気持ちもわかる。
でも、それって本当に大丈夫?と思い始めたら、
講座の構成どころか、
自分のスタンスそのものまで見直すことになりました。
…というわけで、今回はちょっと真面目に、
でも最後は笑えるように、
そんな“型紙との向き合い方”について綴ってみたいと思います。
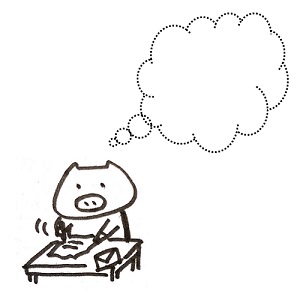
みんなが通る道、「市販の型紙」
私の講座では、「原型から〜」という本格的なことはしていません。
もちろん、そういう部分をしっかり学ぶことは大切であり
原型が引けたら、洋服作りの幅もぐっと広がり、
よりプロの仕上がりに近づけることができます。
わたしも型紙を書くのは、わりと好きな方。
だからあれこれやりたい気持ちもある・・・。
それでも現実問題として、
今の洋裁初心者さんが、そこからスタートするのはハードルが高すぎる。
そこで頼りたくなるのが、市販の型紙や、洋裁本についてくる実物大型紙。
これはもう、みんな一度は通る道。
私もそうでした。
やりたい気持ちもありながら、やっぱり型紙作りは手間がかかる・・・💦
「写すのが面倒だから、切って使っちゃった」
「本の型紙、サイズがないから市販の買っちゃった」
「とにかく早く作りたいから、探してポチった」
──わかる。ものすごくわかる。
時間は有限。
とくに子育てや仕事で忙しい人たちにとっては、合理的な選択です。
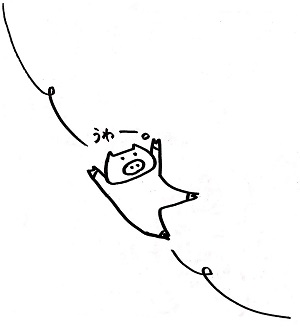
だけど…講師としては見過ごせないこと
でも、ここでちょっと冷静に考えてみました。
自分で楽しむのはOK。
でも、「講座で使っていいの?」って話です。
つまり──
営利目的で市販の型紙をそのまま使って、作り方を教えるのって、どうなんだろう?
もちろん「全部一からオリジナルで作れ」なんて・・・
できたらやりたいけれど、そんな大きなものをコピーすることはちょっと難しい。
でも、「無断でそのまま使って、生徒さんにコピーを配って、講座料をいただく」
っていうのはさすがにダメ。
だから、市販の型紙をそれぞれに購入してもらった上で
作り方のみ教えて講師料をいただく。ってのはどうなの?と思うわけです。
みんな型紙をそれぞれ買っているのだから、いいのではないか???
という気もします。でもそれ正しい???
実際、市販の型紙って、驚くほど著作権について触れられていないものも多くて
使用条件が明記されていないことも多いからこそ、
このようなグレーゾーンが生まれるのではないでしょうか。
「グレーだからいいでしょ」は、
でも講師として、通用しないんじゃないかなと思うのです。
なにより私が型紙を作っている側なら、許せないよね💢
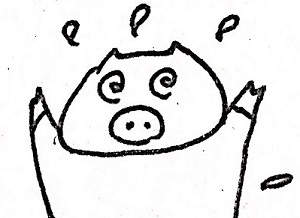
だから直接聞いてみた。。。
そう思った私は、ちゃんと問い合わせてみることにしました。
講座での使用を検討している型紙について、
いくつかの会社にメールを送ったんです。
正直、ちょっとドキドキしました。
だって返答によっては講座の構成を変えなきゃいけない。
で、返ってきた返事は──見事に・・・割れました。
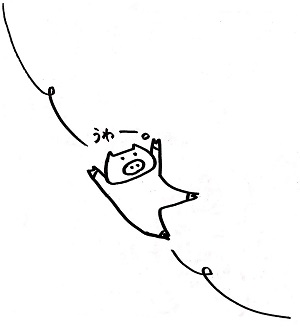
分かれた対応~神対応と門前払い
◎ ある会社は、こう答えてくれました。
「はい、大丈夫です。型紙の著作表示を明記していただければ、
講座でお使いいただいて構いません」
もう、この瞬間、こちらが恐縮するくらい丁寧でありがたかったです。
お忙しいなか、きちんと内容を読んでくださったうえで、
誠意ある返信をいただけたことに、心から感動しました。
文章のトーンもやわらかく、こちらの立場をきちんと理解してくださっていて、
「こんな会社の型紙なら、生徒さんにも自信をもって紹介できる」──
そう思って、次の講座で使わせていただくことを即決。
応援したいと思える会社と出会えた気がして、じんわりうれしくなりました。
× そして、別の会社。
「営利目的での使用は禁止です」
要約するとそれのみで終わり。
つまり「うちの型紙を使って講座をしてはいけない」ということらしい。
終了。
いや、ルールを守るのは当然です。もちろんです。
でも、返ってきたのは“質問に対する答え”というより、“機械的なお断り”。
まるで「そういうこと聞いてくるなよ」って言われたような冷たさでした。
せめて、「お気持ちはありがたいのですが…」くらいのクッションがほしかった。
ちょっとした言い回しで、
受け取る側の気持ちってずいぶん違うのになあ、なんて思ってしまいました。
で、その夜──
モヤモヤを抱えながら、ブログからその型紙の名前とリンクを無言で削除。
それも静かに、執念深く(笑)
いや、そこまでしろって言われたわけじゃないんですよ? もちろん。
でも、なんかもう……こう、感情のやり場がなくてですね。
「はいはい、わかりましたよ、
こっちは田舎の小さい洋裁教室ですけどね」ってちょっと卑屈になって、
「どうせ使っちゃダメなんでしょ」って逆ギレして、
「もういいよ、ぜんぶ消してやるぅ〜〜!」ってやけくそ(笑)
でもまあ、落ち着いて考えれば、向こうにも事情はあるし、
これはこれでひとつの線引きなんだろうな、とも思います。
※もちろんどっち?使っていいの?ダメ?っていうような曖昧な返信のところも正直ありました。
その場合は、ちょっと様子見でしょうかね。
はっきり断られたわけじゃないから、この場合はグレー💧またグレーか(-_-;)トホホ
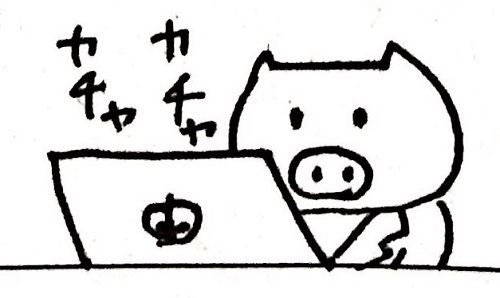
伝えたいことは、怒りじゃなく「誠実さ」
別に、ダメって言われたから怒ってるわけじゃないんです。
ただ、「教える人が責任もって扱うつもり」って事を、伝えたかった。それだけ。
だって、市販の型紙は作った人の技術の結晶。
それを“使わせてもらう”立場である以上、
ちゃんと許可を取って、感謝して、使わせてもらいたいんです。
だから、私の講座では、
今後も「OK」と言ってくださった型紙のみ使用します。
参加される皆さんには安心して学んでもらえる場所にしていきたいですからね。
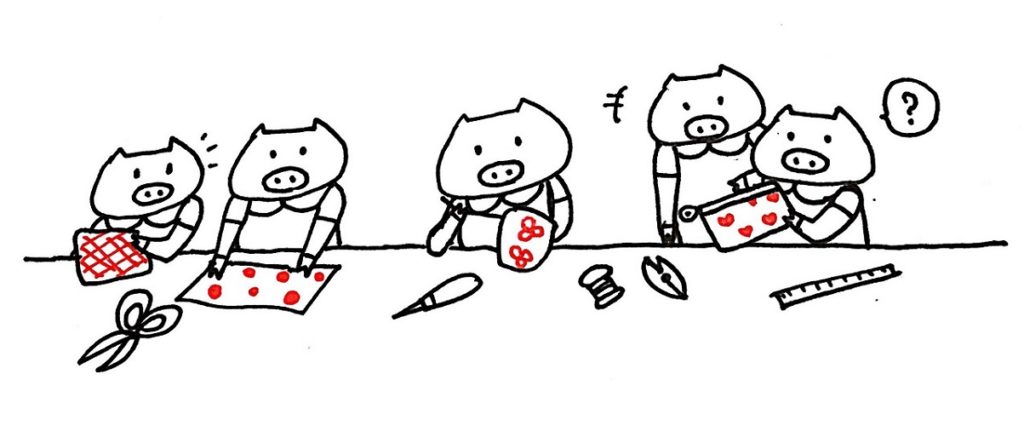
講座の存在意義を、もう一度信じたい
そもそも──
市販の型紙ですが、
これを使って作ろうと思っても、説明書が難解すぎること、ありませんか?
いったい何を言っているんだい???みたいな💧
「縫い代つけて裁断」って、え?どこに?何センチ?
「表に返す」とか、「中表で縫う」って、
図がなきゃ(あったとしても)初心者にはハードル高すぎ。
だから私は、自分の講座では、
本や型紙に付いている説明書をしっかり読み解きながら
わかりやすく、ていねいに伝える。
自分ひとりでも、説明書を読んで理解できるようになってほしいと思っているのです。
そのためには、まずは講師が誠実でありたい・・・と。
地味だけど、誠実さを忘れずに、
ひとつひとつ積み重ねていくしかないんだろうな、と改めて思いました。
たとえそれが、誰にも気づかれないような小さな選択でも、
「ちゃんと筋を通しておく」って、
自分の気持ちをスッキリ保つためにも大事なこと。
それに、受講してくださる方には、安心して学べる場所であってほしい。
だからこそ、「この型紙は使っても大丈夫」という裏付けがあることで、
教える側も学ぶ側も、気持ちよくその時間を過ごせると思うのです。
……そしてやっぱり、「迷ったら直接問い合わせる」が一番確実。
曖昧なままにせずに確認することで、
無用な不安も、変な気まずさもなくなります。
……なんて、ちょっとまじめに語ってしまいましたが。
実際は真夏の夜中に、ブログのリンクを無言で削除してるっていう
恐ろしい光景がありました(笑)
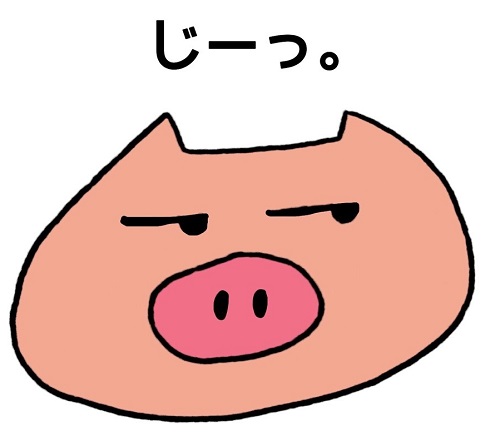
講座の裏では、そんな静かなる型紙騒動があったのでした。
で、どの会社が×で、どの会社が◎だったのか?
それは……今、サイドバーに生き残っているリンクたちをご覧ください。
リンクがごっそり消えていたら──察して、ということで(笑)
型紙を無料でくれと言ったわけでも、勝手に使わせろとも言ってない。
ただ、ちょっと聞きたかっただけ。
講座のために、確認したかっただけなんです。
だから、あのテンプレ返信が来た瞬間──
「あ、こっちは大事にされてないな」と、静かに察しました。
こっちも学びました。
今後は、丁寧な対応をしてくれる会社の型紙だけを使います。
その方が、こっちも気持ちよく教えられるし、
生徒さんにだって自信をもっておすすめできる。
信頼って、リンクと同じで、消すのは一瞬。
でも、築くのは、けっこう手間がかかるものですね。
いや今回の場合は、はじめから信頼されていたわけでもないしね💧
こっちが勝手に、この型紙いいなーと思って使っていただけで💧
──というわけで、夜中のリンク削除劇。
あれはただの“気まぐれ”じゃなくて、
私なりの「これは要らない」と思った静かな線引き、でした。
さ、今日も気持ちよく、信頼できる型紙で講座、やっていきましょうか。
ではまた♪




コメント